彫刻家のダリのような見た目の男。
彼の背中を追って、私は院内の中央に設けられた螺旋階段を上る。
渦を描くような螺旋は、まるで私の思考・心理を映しているようでもあった。
ひとつ気になることがある。
白衣姿のダリの隣に控えたもう1人の男だ。
彼はまだ一言も発していない。
ただダリの横に追従しているだけだ。
白衣を着ているものの、頭にはフードを被っているため、顔が見えない。
医者が顔を隠すなど、あり得ない話だ。
その手には分厚い医学事典が握られている。
あまりにも意味の分からない状況に、私は戸惑っていた。
「あの、これからどちらへ?」
「決まっている。お前に担当してもらう患者のところだ」
白衣姿のダリは答えた。
「この格好でですか?」
私はスーツに身を包んでいる。
「いいのだよ。挨拶だけなのだから」
私はそこで、まだお互いの名前も知らないことに気付いた。
「そういえば、申し遅れましたが、私、本日からこちらで……」
「いいのだよ。知っているのだから。俺は霧山妙(きりやま みょう)。ここの院長を務めている」
霧山は被せるようにして返答した。
「そうでしたか。どうぞよろしくお願……」
「それで、お前に担当してもらう患者の話だが、彼女は『精神過剰症』を患っている」
どうやら、この男は人の話を聞かない性質らしい。
それにしても、『精神過剰症』?
なんだそれは、聞いたことがない。
「精神過剰症ですか……」
「なんだ、そんなことも知らんのか。下らん奴だ」
「申し訳ございません」
初対面の相手に「下らん奴」とは、随分と失礼な人間だ。
「簡単に言えば、通常の人間よりも喜怒哀楽が激しいのだよ。あらゆる感情に対して我々は通常、ある程度の抑制をかけている。しかし、彼女の場合、そういうものは一切ない」
「はぁ、なるほど」
それまで歩くのに徹していたもう1人の男が、唐突に医学事典を私によこした。
開かれたページには、たしかに精神過剰症の記述があった。
「つまり、感情の蓋がないということだ。理解したか? 理解したな」
「は、はい」
本当にせっかちな男だ。
この男こそ、診察を受ける必要がありそうだ。
霧山は螺旋階段をおりて、2階の廊下を歩き始める。
建物自体が円筒形で、吹き抜け構造になっているため、どのフロアの廊下も曲線を描いている。
「霧山院長、そちらの方は?」
隣に立つ奇妙な男の存在が気になり、私は思い切って尋ねてみた。
「ああ、気にするな。私の助手だ」
「そうですか……」
不服そうな私の声を聞いたためか、霧山は何の予備動作も見せずに、くるりと振り返った。
「そうか、お前は非常識だと思うか?」
「え? はい、まぁ、顔を隠すのはどうかと思いますし、どうにも私には……」
「そうか、ではこうしてみよう」
そう言って、霧山は男の耳元で指を「パチン」と鳴らした。
「……ぎぎぎがぎゃあああああああああ!!!」
隣の男は狂ったように大声を上げて、螺旋階段に戻ってしまった。
医学事典だけが、その場に落ちている。
「彼は、どうにも破裂音が苦手らしい。しかしどうだね? 我々にとって、指を鳴らす音など気にもならないだろう。だが、彼にとってはそれが脅威なのだ。彼にとっての常識では、その音は危険信号なのだよ。私が紐解く恐怖と、彼の紐解く恐怖、そしてお前が紐づける恐怖は全てが異なる。全ての人間が全ての人間にとって非常識なのだ。常識などその程度のものだとは思わんかね? お前に必要なのは、何が常識で何が非常識なのかの線引きなどではなく、お前の常識とルールとしての常識にどれだけの乖離があるのかを意識することだ」
「はぁ……」
突然何を言い出すかと思えば、全く脈絡のない話だ。
だいいち、私の質問には一切答えてくれていない。
納得できずに、歩き続けていると、まともや唐突に霧山はある部屋の前で立ち止まった。
あまりに急停車したものだから、思わず背中に衝突してしまった。
「ここだ」
205号室。
それだけは読み取れた。
しかし、銀色のネームプレートに書かれた文字は酷く劣化しており、判別ができない。
名前が分からない。
霧山が部屋をノックしようという段になって、院内放送が流れた。
「霧山先生。至急305号室へお越しください」
この部屋の真上か。
たしかに、ドタバタと騒がしい音が天井から聞こえる。
「くそ、またか」
霧山は舌打ちをしてから、階段の方へ向かった。
「あ、あの。私は、どのように?」
「先に挨拶を済ましておけ。ああ、忙しい忙しい」
一度歩き出した霧山だったが、思い出したかのように振り返る。
「言い忘れていたが、彼女を担当した医師はなぜかことごとく死んでいる。なぜか、マンガ喫茶で死んでる者までいた。意味不明だろう。お前も少しは気を付けることだ」
「え?」
霧山はそれだけ言って、その場を去っていった。
「なんなんだ、一体」
その場に立っているわけにもいかず、私はドアをノックして、病室へ入った。
そしてそこには、混沌が広がっていた。











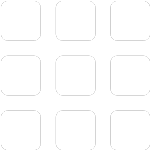








コメントを書く