三島看世との散歩を済ませてから、私は不機嫌な表情で、305号室へ向かっていた。
看護士など一人もいないナースステーションで、ミズの点滴パックを手に入れて、ミズの部屋へと移動する。
3階まで到達したとき、誰かの後ろ姿が見えた。
しかし、私の視界に残っていたのは、その人物の後ろ足だけで、姿を完全にとらえる前に、305号室とは反対側の部屋に消えてしまった。もしかしたら、どこかの患者が抜け出してしまったのかもしれない。そうなると、連れ戻す手間が発生する。面倒な話だ。
不気味なまでに白く輝く床には、私の歪んだ表情が映し出されていた。
木ノ下雪からのお願いとはいえ、あの暴力的なミズに会うことを考えると憂鬱になる。
小さくため息を吐いてから、305号室の鍵を開けようとした。
だが、手応えがない。鍵を解除したときに感じるあの感触がない。
おかしい……と思い、扉に手をかけると、扉は簡単に開いた。
つまり、誰かが鍵をかけ忘れていたようなのだ。
ミズはその狂暴性からして、必ず部屋の鍵をかけなければならないのだが……
木ノ下雪は心配性な性格なので、彼女が鍵をかけ忘れたとは考えにくい。
ほかの医師か、霧山院長がかけ忘れた可能性はあるかもしれない。
私は2回目のため息を吐いてから、半開きになっている扉を全開にした。
と、そのとき、部屋に入り、扉が閉まりきったそのとき、突然ミズが襲いかかってきた。
ベッドに縛り付けられているはずのミズの四肢に拘束具はなく、野に放たれた野獣のように私という獲物に飛びかかってきたのだ。
私は腰を抜かし、ミズの力によってその場に押し倒された。点滴パックは落ちて、室内の奥に転がっていく。
ミズは私の体に爪を食い込ませ、その細身からは考えられないほどの凄まじい腕力で私を床にねじ伏せる。
ミズの右手にはどういうわけかホースが握られていた。
ホースは室内に設置されている洗面台の蛇口に繋がっており、大量の水が流れ出ている。
「水! 水! 水!」
目を血走らせながら、ミズは私の口にホースを押し込んできた。
「な、やめろ! なぜ、お前は……」
体をばたつかせて、ミズを退けようとしたが、その怪力の前に私は為す術もなく、口に大量の水が注ぎ込まれていく。
「死! 死! 死!」
ミズは支離滅裂な言葉を私に投げつけてくる。
口から侵入した液体は間もなく、鼻から吹き出し、胃の中にも溜められていく。
酸素が不足し、自分の腕が青く染まっていくのが見える。
このままでは死ぬ。間違いなく死ぬ。
私はミズの体を蹴り飛ばしていた。
脚の力にはさすがのミズも抵抗できず、ミズの体は部屋の真ん中へ転がっていった。
「ぶべら、ぶべら……」
訳のわからない文字を口から垂れこぼして、ミズは腹を押さえて蹲る。
「げほ、げほ……」
私は胃の中に紛れ込んだ大量の水を吐き出した。
だが、落ち着いてもいられない。
ミズは体勢を立て直して、もう一度私のもとに突っ込んできたのだから。
意識が朦朧とする中、私はポケットに潜ませていたライターを取り出し、ミズの前で点火した。
「火! 火! 火!」
火に対して強い恐怖心を持っているミズは、頭を抱えながらその場に丸まった。動きが止まったのだ。
「なぜ自由に動き回っているんだ! 誰がお前を解放した? なぜホースなんて持ってる? 答えろ!」
「火、火、火! でも、黒い、黒い、瞳が、第サンのヒトミ、死が!!」
ミズは突進してきた。
火を極度に恐れるミズが火に向かってきたのだ。
私はあまりに予想だにしないミズの突進に驚き、ライターをミズの顔に押し付けた。
皮膚が焼けるじゅうという音が振動とともに私の手に伝わってくるが、ミズはお構いなしだ。
腕を振り回しながら、私の懐に踏み込んでくる。
全体重をのせるように拳を私のこめかみに突き立てる。
不意に飛び込んできた拳が脳天を直撃し、私は扉まで押し戻された。
私は扉を開けようと、ドアノブに手をかけた。
「……開かない、くそ! どうなってる!」
ミズはまたもや距離を詰めてくる。
このままだと殺される。殴殺される。
死に至る恐怖が全身の血管を循環し、冷や汗がありとあらゆる体細胞から噴き出してくる。
死にたくない。死にたくない。
そのとき、入り口付近のパイプ椅子が目に入った。
「ぷぎゃらぁぁあああ!!」
ミズは奇声を上げて、飛び上がった。
「くるな! くるなぁぁあああ!!」
硬いもの同士がぶつかり合う鈍い音が響いた。
ミズは私の足元に転がり、無様に体を痙攣させていた。
私はミズが飛び込んでくる直前、パイプ椅子を手に取り、思いきりやつの頭部に降り下ろしたのだ。
「おい」
舌を出して泣いているような笑っているようなミズの顔を覗いてみるが、すでに息はなかった。
「……私は悪くない、私は悪くない」
頭を抱えて自分に言い聞かせるが、体の震えは止まらない。
なにせ私は初めて、直接的に誰かの命を奪い取ったのだから。
絞殺された家畜のような乾いた悲鳴が病室に充満していた。











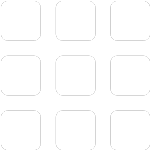








コメントを書く