ほんのわずかな木々の隙間から零れた木漏れ日が、庭の中心部に鎮座するクスノキを照らし出していた。
霧山精神病院の裏手に設けられた庭。
周囲を背の高い常緑樹に囲まれたこの場所では、晴れの日だろうと滅多に光が届くことはない。
ただ、この時ばかりは示し合わせたかのように、枝葉をかいくぐって、クスノキだけを強調するように光が差し込んでいた。
キリキリ、キリキリ……と車いすを押す音が樹木の間を反射し続け、奇妙な反響音が庭全体にこだましていた。
私は霧山院長の指示通り、三島看世を散歩に連れ出していた。
車いすに乗る彼女を、何度か確認しながらクスノキの手前まで、車いすを進めた。
「君は歩けないのか? 足に障害でもあるのか?」
不思議なことにここへ来る前、霧山院長に遭遇し「三島看世は車いすでの移動だ」と告げられたのだ。
ゆえに車いすでここまで連れてきたわけだが、なぜ歩けるはずの彼女にこんなものが必要なのだろうか、皆目見当がつかない。
彼女は白い院内着の裾をぎゅっと握りしめて、笑いをこらえている。
「違うわ、先生。歩けないんじゃなくて、歩いちゃいけないの。わたしはね、大地を踏むと興奮してしまうの。楽しくて、喜ばしくて、たぶん喉が潰れるまで笑い転げてしまうわ」
木々の隙間から流れ込む光の粒子たちは彼女を避けるようにして、彼女の足元や彼女の髪の毛に部分的に付着し瞬時に離れていく。
純粋に明るく照らされることも、不純に暗く沈むこともなく、彼女の姿は光と闇を交互に横断し続けている。
彼女自身の意思ではなく、彼女を取り巻く風景が情景が、自発的に彼女の姿にコントラストをもたらすよう動いているようでもある。
それも相まって、彼女の愉悦に満ちた横顔はより一層妖怪じみて見えた。
「それが精神過剰症なの。些細な喜びでも体が壊れるまで笑ってしまう。でもね、それは本来、自然なことだと思うの」
「お前は、この期に及んで自分を自然な存在だと思っているのか? 自然な人間ではないから、ここでこうして意味のわからん高説を垂れているんだろうが……」
「わたしは別に社会的な人間として自然だなんて言ってないわ。人間として生物として自然だという話。地面を踏みしめることって本来は、とても愉快なことなの。子どもが意味もなく走り回っているのはそのためよ。子どもたちは知っているの、大地が足に触れる快感と満足感をね」
「私にはよくわからない」
「……あなたは大人だもの。感覚を鈍化させて生きる。それが社会で大人として生きるために必要な最低条件だものね。みんな忘れてしまうのよ。自分が人間だったことを、自分が生物だったことを……」
唇に水滴が張り付くような喋り方をしたあと、彼女は何かを発見した。
「あ……」
クスノキの影に隠れるように横たわった1羽の雀だ。
彼女はしきりに車イスを動かして、雀の倒れている場所まで移動した。
手のひらにそっと雀を乗せて、その艶やかな指先で、雀の羽をゆっくり撫でる。
それは死骸だった。
まだ体の腐敗は始まっていないので、死んで間もなくといったところだろうか。
「かわいそう……」
水気を帯びた口許から、クチャクチャと小さな言葉が漏れた。
呪いの小説を書いた人間の言葉とは思えないほど、哀れみと情感に満ちた言葉だった。
「ふん……人殺しが何を言っている」
「この子、たぶん寿命がきて死んでしまったのね」
「自然死だ。誰かに捕食されることもなく、苦しまずに死んだのなら、生物にとってそれは幸せな死に方だと思うがな」
「そうかしら?」
先程までわずかに吹いていた風が吹き止み、無風の空間が広がる。
無風であるがゆえに、彼女の一言一句、一挙手一投足が何にも遮られることなく、例外なく音に変換されて私の耳元に届く。
「わたしには一番不幸な死に方にしか見えないわ」
「何を言っている? 自分の生をまっとうしたんだ。幸せじゃないか」
「わたしたちはね、自分の意思では生まれてこれないでしょ? 誰かがわたしという命に干渉して初めて、わたしはここに存在できる。そこに愛があるの。わたしたちが生まれて初めて知る愛情は干渉なのよ。干渉し干渉されることにこそ、愛の本質があると思わない? もし生命の誕生が干渉によってなされるのだとしたら、死に干渉されることもまた生命が持っている根元的な願望なんじゃないかしら?」
「だから、人殺しも正当化できると?」
「正しいとか正しくないとか、そういう善悪二元論の話ではないわ。愛情表現の話。この子みたいに、誰にも干渉されずに死を迎えるのはあまりにもかわいそうなだけ。わたしは、そんな不幸には堪えられない……」
そのあと、彼女は嗚咽を漏らして泣きわめいた。
たかが雀の死に彼女は、嗚咽し嘔吐した。
全く理解できない姿だと思いたかったが、彼女の殺しと愛情にわずかに共感する自分があることを知り、わたしは生まれて初めて自分を激しく嫌悪した。











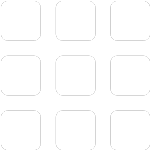








コメントを書く