廊下を流れる水は少しずつその量を減らしていた。
階段を流れ落ちる水音だけは継続され、院内にこだましていた。
野生児ミズの連行される様を見ながら、私は霧山の言葉を待っていた。
「普通の病院でないことは、なんとなくわかりますが……」
そう、普通の病院ではない。
院の構造からして、医者の態度からして、患者への接し方からして、
何一つとして普通などと言えるものはここにはない。
「この場所は名目上、精神病院なんて名乗ってるが、実際は違う」
霧山は長く伸びた立派な髭の両端を、どこからか取り出した櫛(くし)で整えている。
「と、申しますと?」
霧山はポケットに手を入れながら、私の周りをグルグルと旋回し始めた。
その眼球だけは私を凝視しており、視線の牢屋に放り込まれたかのような気分だ。
「ここはな、精神障害を持つ犯罪者を収容している施設なのだよ」
「矯正施設のようなもので……」
「いや違う」
相変わらず言葉をかぶせる癖は健在だ。
「矯正施設とは、犯罪者を社会的な人間に戻すことを目的としている施設だろう? だが、うちの患者たちが社会に復帰することは絶対にない」
「それはどういう?」
「奴らは重度の精神障害を抱えているだけでなく、極めて重い罪を犯している。それはそれは重い罪だ。それこそ海外なら懲役100年はくだらないほどのな。そんな重罪人たちを社会に戻せると思うか? 要するに……」
「終身刑務所といったところでしょうか?」
私の周りを周回していた霧山は、その場で足を止めた。
歯ぎしりしながら、私をにらみつけている。ただでさえ血走っている瞳が余計に充血しているように見えた。
どうやら、私が言葉をかぶせたのが気に入らないらしい。
「無礼かつ失礼な奴め、今は俺が話している」
「す、すみません……」
実に納得がいかない会話だが、そんなことはどうでもいい。
「だが、その言い方でおおよそ間違ってはいない。ここは刑務所だ。それも本物の刑務所では世話しきれなかった問題児が集められている。そして異常行動の観察や新薬の試験体として利用されている。ゆえにここでの仕事は患者のケアではない。囚人の管理だ。試験体の管理だ。理解したか?理解したな?」
それでは話が違う。
私はあくまでも医者として、この病院へ訪れているはずだ。
それが囚人の監視員だったなどと、笑い話にもならない。
「いえ、だとしたら私はここにいるべきではありません。私は医者です。医者として勤務するのであればともかく……」
「ほう……人を殺しているのにか?」
霧山はすり足で私に近づき、いまにも額が接触するのではないか、というほどその自己主張の激しい顔面を私の眼前に突き出してきた。
背中を通る冷汗は、重力によって足元まで沈殿し、私の足は水浸しになっている。
ミズの流した水流はすでに、なくなりつつあるのに、靴の中には脂汗の沼が形成されていた。
「やはり、ご存じだったのですね……」
「お前は一体、何人の人間を殺してきた?愛人、娘、妻……そんな殺人狂が働ける場所などあると思うか?」
「ち、違う。娘や妻は……」
「これでもそう言えるのかね?」
霧山は白衣のポケットからスマートフォンを取り出し、そこに写真を表示させた。
そこには、私が庭に死体を埋めている姿や、海岸で骨をばらまいている姿。
「なぜ……どうやって。一体いつ……」
「どちらにせよ、愛人を三島看世の母、三島美佐を殺した事実は変わらない。いくら罪に問われないとしても、お前が生きていく世界などもはやここ以外に残されてはいない。今は一人でも人員が欲しい。誰であろうと構わない。患者を殺してしまうような犯罪者だろうと問題ない。なぜなら、患者もまた犯罪者だからだ。ここはそうやってできている施設なのだ」
天窓から差し込んだ月光は、私の肌を撫でてから、真っ白な床を照らし出した。
異常なまでにワックスのかけられた床には、私の歪んだ顔が映し出されていた。
悲痛や悲嘆を込めた悲鳴じみた苦痛にもだえる顔だった。
社会の上位に君臨していた男の顔とは思えなかった。
いや、地位があったからこそ、この苦々しい顔が生まれるのかもしれない。
床に映された私の顔に、鍵が投げ込まれた。
霧山が鍵を落としたらしい。
鍵には「803号室」という部屋番号が刻まれている。
「お前の部屋の鍵だ。今日は挨拶だけなのでな、あとは好きに過ごせ。患者のカルテは1階のナースステーションにある。読んでおけ、三島看世のカルテもそこにある」
そう言って、霧山は足早に上の階へ消えた。
床に落ちた鍵を拾い上げると、指先に痛みが走った。
鍵には棘のようなものがついており、それが親指に食い込んだらしい。
私は即座にその先端を踏みつけて、折ることにした。
親指からは血が流れだし、床に映されたみじめな男の顔にぽたぽたと落ちていく。
親指から何かが流れ込んだような違和感があった。
血管に寄生虫が入り込んだかのような妙な感覚が腕にひろがっていった。











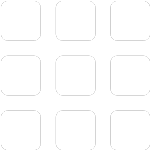








コメントを書く