丸山道尾が悪夢にうなされている頃。
霧山精神病院の一室、野生児ミズの病室に、小さな足音が近づいていた。
頑丈な鎖で四肢をベッドに縛り付けられているミズ。
痩せ細った両手両足をばたつかせて、その拘束具から逃れようとするも、伽藍洞のごとく何も置かれていない室内に鎖同士の擦れる音がただむなしく反響するだけで、いかに細身でありながら豪腕な彼でも自由になることはできない。
彼が暴れているのには訳がある。
先ほどから聞こえる小さな足音。
ペタペタと耳に張り付く、水気を帯びた足音。
背中に流れる冷汗と、全身に感じる嫌な気配。
この闇の接近にミズは本能的に怯えていた。
裸足が床に張り付く音。その音は、305号室、ミズの部屋の前で止まった。
同時にドアがゆっくりと解放され、真っ白な肌の女が立っていた。
ミズはもう一度、四肢をばたつかせるが、女はミズの拒否反応などお構いなく、スルスルと今度は足音を立てずにベッド脇まで移動する。
月明かりに照らされた横顔、それは三島看世のものだった。
顔を認識した瞬間、ミズの動きは止まった。
いや、硬直したのだ。彼女の威圧感とも圧迫感とも言える異常なまでに澄み切った白肌と奇妙なまでに開かれた眼球を前に、ミズは体を動かすことを制限されてしまったのだ。
当然、ミズに看世という女を認識するだけの認知能力はない。
しかし、本能的に危険だということは十二分に理解していた。
むしろミズだからこそ理解できたのかもしれない。
野生児だからこそ、感覚の鈍化した都会人ではなく、感度の高い野生児だからこそ唯々諾々と流れ出る看世の危険の香りを嗅ぎ分けることができるのかもしれない。
ミズは顔をただ震わせながら、「あがあが」と言葉にならない小さな悲鳴を口から零す。
看世はそんな怯えるミズの顔を優しく手で包み込む。
不必要に頭の先から喉仏まで撫でまわしていき、ミズの震えが静まった時、その手はミズの頬に食い込んでいた。
頬に爪を突き立てる。闇の中に流れるで赤黒い液体が看世の爪を艶やかに染めていく。
看世は片手に持っていた本を開いた。
本のタイトルは『第三の瞳』である。
看世は本をミズの眼前に広げて一ページずつ丁寧にめくっていく。
ミズは息を荒げながら、本に目を通していく。
理解できるはずもない、本の内容に眼球が吸い込まれていく。
ミズの中でも、今の自分の行為が自分の生存にとって危険だという認識はあるのだ。
あるのにも関わらず、目が離せない。
あらかたページをめくり終えて、看世は本を閉じた。
「可哀想ね……あなた、死んでしまうのよ」
「シ、シ、シ……しぬ? いやだ……嫌だ!!!」
「なら、ちゃんと言うこと聞いて」
「キ、キ、キ、キく」
「いい子ね、あのね……」
看世はミズの耳元に唇を近づけて、ペタペタと一言だけ告げた。
素直にうなずくミズ。
「さて、これで彼女は救われるかしらね、でも、それもあなた次第よ……」
看世は満足げに微笑んでから、病室を出ていった。
ミズのベッドは濡れていた。
恐怖に誘引されて、排尿してしまったようだ。
やるべきことが定まったミズの目には、血の線が無数に張り巡らされていた。
廊下には看世の足音がもう一度響き渡る。
看世はエレベーターに乗り、上層階を目指していた。
エレベーターは8階でストップした。
丸山道尾が眠る、8階でストップしたのである。











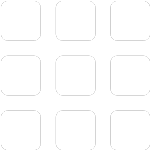








コメントを書く