本質は実存に先立たない。
そんな風に言われたかのような錯覚を覚えた。
意味付け……三島看世と私の間にはどんな意味付けが存在するのだろうか。
医者と患者、容疑者と被害者、男と女……
頭の中と心の中に姦しい会話を響かせながら、私は螺旋階段を上っていた。
4階の資料保管室。1日の大半は、その部屋で過ごすことになる。
ここでの仕事はどうやら、患者のケアというよりは、日々行われる投薬治療や臨床試験とは名ばかりの人体実験で得られたデータをまとめる作業がメインらしい。
4階を目指して螺旋階段を上っていたところ、3階で1人の女が立っているのが見えた。
真っ赤な色の派手なヒールを履いた女。昨日8階で遭遇した木ノ下雪であることは、遠目からでもすぐにわかった。
彼女は階段に背中を向けるように、305号室の前にしゃがんでいた。
何をしているのだろうか?
もしかしたら、何か落とし物をして探しているのかもしれない。
あの部屋はミズの部屋だ。
ミズから暴行でも受けて、顔に傷を負ってしまい、そのせいで蹲っているのかもしれない。
私は唐突に木ノ下雪が心配になった。
過去に人を殺しておきながら、今は人の心配をしていた。
それはひとえに、彼女の放つ色香に誘われて生まれた感情であることは間違いないけれども、ここで全く何の反応もできないのであれば、私はとっくに自分の性について「男」と記入することもなくなっているはずだ。
「あの……木ノ下先生」
「え?!」
跳ね上がった。
バランスをとるには頼りないヒールは脱げて宙を舞い、私の足元まで転がってきた。
突然声をかけられたからだろう、彼女は驚いて瞬間的に身体を跳ね上がらせ、足を滑らせたあげく、その場に尻餅をついてしまったのだ。
「す、すみません……大丈夫でしたか?」
極めて紳士的に私は彼女へ手を差し伸べ、かつ動揺した様子で彼女へ喋りかける。
なぜ人は動揺した口調で話すのか。
それには大きく2つの理由がある。
1つは本当に驚いているから、あるいは動揺しているからだ。
もう1つは、自分は社会性のある人間だと相手に認識してもらいたいからだ。
驚くべき場面、動揺するべき場面、うろたえるべき場面……
我々の社会ではどの場面でどのように反応するべきかが、あらかじめ決められている。
どもったり、噛んだり、転んでしまったり……
感情の表し方は、初めから限定されているものである。
その場面に即したリアクションを行うことで、我々は相手を同じ共通概念としての社会性を持った人間であると判断する。
私が動揺する動機は、たいていがこの理由からきている。
決まりきった反応をすることで、「あなたと私は同じ常識の範疇に属しています」という意思表示になるのである。
とはいえ、これが通用するのは常識人だけだ。
常識人の中において、常識は常識として機能するが、非常識人の中で常識は単なる言葉の羅列としてしか認識されない。
三島看世がそうだ。こうした社会通念は彼女の嫌うタイプの意味付けであり、彼女の前で常識は、紙切れか石ころに過ぎない。
彼女の場合、意味は社会の側ではなく、常に彼女の側にあるのだから。
不必要にワックスのかけられた床には、木ノ下雪の下着が映っていた。
肌を隠す役割を果たしているとは言えないほどスカスカの下着に、私の目は反射的に吸い込まれそうになったが、そのことに気が付いたのか、彼女はスカートと床に手のひらをかざして、一瞬だけ微笑んでから立ち上がった。
「ごめんなさい、あたしビックリしちゃって」
少し崩れてしまった長髪を指でほぐしながら、彼女はもう一度にこりと笑った。
「い、いえ。私のほうこそ申し訳ありませんでした」
そう言って、私は拾ったヒールを彼女の足元に戻した。
「拾ってくれたんですね! ありがとうございます」
「それで、木ノ下先生はこちらで何を? 落とし物でもされたんですか?」
「あ……ちょっと、ミズくんに」
彼女の腕には歯形がつけられていた。
どうやら彼女は何かしらの理由で、ミズに噛まれてしまったらしい。
さっきつけられたにしては、随分と古い痕にも見えるが。
「大丈夫ですか?」
「心配しないで、丸山先生。よくあることですから」
「ですが……」
「そうそう! ちょうどよかった。丸山先生に1つお願いしたいことがあって」
「なんでしょうか?」
「お昼過ぎでいいんですけど、ミズくんの点滴だけ代えておいてもらえませんか?」
「いいですよ、そのくらいでしたら」
「よかった、丸山先生、優しいですね」
包み込むように手を握ってから、彼女は背を向けて歩きだした。
と思いきや、もう一度私のほうへ戻ってきた。
「あ、忘れないでくださいね。ミズくん点滴がないと、栄養摂取できないから」
念押しか。
「心配しないでください。必ず代えておきますから」
「ありがとうございます、あたし、結構心配性で」
心配性の木ノ下雪は私に一礼してから、かたかたとヒールを鳴らしながら、階段を下りて行った。











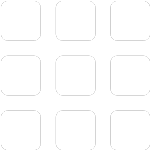








コメントを書く