壱
身体全体に余計な重力がかかっていた。
特に腕はひどい。脳の指令に従って、反応することはできるが、電気信号の送受信が極めて緩慢で、腕が上がり切る前に、だらりとだらしなく垂れさがってしまう。
休憩室のベンチに腰掛けながら、私はこの世の誰よりも猛烈にうなだれていた。
頭も腕も、いや身体そのものが、地面と融合してしまうかのように、力が抜けきっていた。
本来は青色のベンチが私の沈んだ影のせいで、黒く染まっているように見えた。
白い壁に囲まれた空間で、私だけが黒かった。
室内に備えられた自動販売機から、缶の落ちる音が響いた。
「丸山先生……先生のせいではありませんよ」
かすかに動く右目を利用して、目の前に立っている木ノ下雪を見上げる。
彼女は私の隣にさりげなく座った。
膝を折りたたんで、足を横に流しながら、スカートの裾を右手でするりと整えて、私を覗き込んだ。
「丸山先生、自分を責めないでください。ほかにも、こういう事例はありますし……」
私の腕には、パイプ椅子を持った時の重量感と、それで彼を殴りつけたときに覚えた生々しさが、ありありと残っていた。
「彼はどうなるのでしょうか?」
「裏の庭がありますよね? あそこに埋められます。もともと身寄りのない子でしたから、それくらいしか……」
裏庭とは、あのクスノキが佇む神秘的で不気味な空間のことだ。
「そうですか」
「丸山先生……」
彼女は眉を顰めながら、困ったような顔で、心配したような顔で、私の下がり切っている顔と同じ高さまで顔を下げて、私を見る。
潤んだ瞳で、ハイライトが揺らめく瞳で、油分を多分に含んだ瞳で、私を見る。
腹の底が少しうずく。こんな時なのに、私の腹の底に欲望が沈殿していくのがわかる。
「私は人をこの手で……」
これは告解なのだろうか。いや、違う。私の絶望を彼女に共有したい。その願望が現れているのだ。
自分の気持ちを理解して欲しい。あわよくば癒して欲しい。私らしくない極めて受動的な欲望だ。
私らしくない……
心の中でつぶやいた言葉だったが、自分の出した表現に大きな違和感を覚えた。
三島看世の言う通り、私は社会から意味付けされて生きてきた。
自分自身で自分を規定するのではなく、社会の側から規定されることで、自分を自分たらしめていた。
だとすれば、私はいつから、私らしくなくなったのだろう……
私はいったい誰の代理人なのだろう……
そんな弱気な私の心に割り込むようにして、木ノ下雪は私の頬に水気のある指先をくっつけてくる。
「大丈夫です。丸山先生は不可抗力だったんですから。特に処分はないはずです。これ……よかったら」
彼女は缶コーヒーを手渡してきた。
「……すいません」
私は缶コーヒーを受け取った。
と、彼女はそのまま私の手をぎゅっと握った。
私の凸凹な手を、最上級のシルクが包み込む。
手の甲に彼女の指紋がべったり張り付いていく感触があった。
「丸山先生……こんな時にあれかもしれないけど。いえ、こんな時だからこそ、心を休めるためにも近くの街に出かけませんか?」
「え? そんなことできるんですか?」
「行ける場所に制約はありますけどね。ほら、丸山先生もここへ来るとき、途中でタクシーを乗り換えた街がありませんでしたか?」
「そういえば……」
「あそこなら外出許可が下ります。ショッピングモールとか、映画館とかいろいろあるんですよ? 行きませんか? もし嫌でなければ……」
そう言って彼女は私の太ももに指を這わせた。
「はい……」
自分の意志で出したとは言えないような吐息を漏らして、私は木ノ下雪からの誘いを受けた。
冷たいはずの缶コーヒーから生温い温度を感じた。
弐
それは奇妙な街だった。
霧山精神病院から車で約30分、九十九折りの山道を下りた先に広がる盆地にはミニチュアの街があった。
四方を山に囲まれた閉鎖空間のような場所だ。
重たい深緑色の木々たちがその街を眼下に眺めている。
霧山精神病院から専用のダイヤルにつなぐと、タクシーが私と木ノ下雪を迎えに来た。
私たちはそれに乗り、市街地へと移動したわけだ。
山に囲まれたその街は街自体も大きな塀で囲まれており、街全体が刑務所のようであり、しかしその華やかさからすると、アミューズメント施設のようでもあった。
罪を犯して入る囲いが刑務所であるのなら、非日常を求めて自主的に入る囲いがテーマパークだと言える。
果たして、この街はいったいどちらに分類されるのだろうか。
「阿頼耶識街」入口にはそう記されていた。
街角でニヤニヤしている若者。
不自然なほどに黒い隈を目の下に携えた女。
手をだらりとぶら下げながら歩く不審な男。
正常そうに見える人間たちの中には、ところどころに異常な人間が紛れ込んでいた。
それはほとんど、霧山精神病院の延長にあると表現しても過剰ではないような風景だった。
入口を過ぎてすぐから、私は言い知れぬ不安を覚え始めていた。











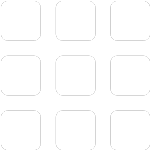








コメントを書く