デバイスの明かりを強くした時、まず俺の目に飛び込んできたのは、死体の山だった。
おそらく、彼女のようにここへ歩いてきた旧人類たちの死体だろう。
白骨化しているものから、まだ肉片が残っているものまでさまざまだ。
「どうしてこいつらは……」
と思い、ライトを奥へ向けた。
するとそこには、無数の氷の人形が列をなすように並べられていた。
「これは、いったい……」
数えきれないほどの人形たちは、それぞれ全く違う形をしていた。
笑っているもの、怒っているもの、泣いているもの、手足がないもの、裸のもの、本を読んでいるもの。
一つとして同じ表情のものがない。
横幅30メートル近く、奥行きは計測できないほど広大な空間に、隙間なく人形たちは佇んでいる。
「ヨルハ、見えてるか?」
「ええ……」
あれだけ、お喋りなヨルハも口をつぐんでいる。
「デウスシステムにこの映像を送れるか?」
「あ、ええ……。さっき送ったわ。でも……」
「どうした?」
「シークレットが表示されたの」
「なに? またか……なんだって、デウスシステムは情報を開示しねーんだ?」
俺たちが驚いていることなど露知らず、旧人類の彼女は氷の人形を列の先頭に立てていた。
震えている手にはしもやけが見られ、瞳の焦点も合わなくなっている。
彼女は氷の人形を立て終えると、その場に崩れ落ちた。
「おい!」
俺はすぐさま駆け寄り、彼女の体を両腕で支えた。
まるで枯れてしまいそうな花のように、彼女の体から力が抜けていく。
「あ、りがと……」
歴史以外の言葉を彼女が初めて口にした瞬間だった。
彼女は、かつて見せたあどけない笑顔を浮かべてから、息をひきとった。
俺の腕のなかの体はだらりとなり、重さがずしりと伝わってくる。
たかだか、10ヶ月しか一緒に過ごしていなかったが、死を見たことのない俺は、別の重さを全身に感じていた。
ケプラーでは、自分が望む限り永遠に生き続けられる。
体が死んでもデータを残し、別の肉体に移植する。そうして、ケプラーの連中は生きている。
だから、誰も死という概念を知らない。
俺やヨルハはまだ、生まれたばかりのようなもので、データの移植を経験したことはない。
だからなのか、彼女の死は、紛れもなく、「死」そのものであるように思えた。
虚無感が去来するなか、洞窟内に外から風が吹き込んだ。
猛烈な風が氷の人形たちを揺らし、独特な反響音が響き渡る。
それはまるで、ひとつの巨大生物が泣き叫んでいるような、存在を誇示しているかのような声だった。
過去に置かれた人形たちから連なる音が先ほど置かれた彼女の人形とハーモニーを奏でている。
俺は立ち上がり、その音色とも、悲鳴とも、歓喜ともいえる風音を体全体に受けた。
「そうか、そういうことか……」
この過去から現在、そして、未来へと吹き抜けていくこの共鳴音こそが彼女たちのいう「レキシ」だったのだ。
このなかの人形がひとつでも欠けてしまったら、それはまた違う音になるだろう。
歴史とは事実の羅列などではなく、それぞれが奏でる音の集合体なのだと、俺は理解した。
「ロウ……。ロウ!」
ヨルハの声で、はっとした。
「ああ、悪い」
「もう、心配させないで」
「ああ。ん? あれは……」
俺はライトを消し、洞窟の奥に目を凝らした。
薄暗くはあるが、奥から明かりのようなものが漏れている。
「どうして、こんな奥地に明かりなんか」
「ロウ、あんまり奥に行かないほうがいいわ。この先の情報が真っ白なの」
宇宙服の頭部のディスプレイに、マップが表示されていたが、洞窟の奥は何もないことになっていた。
「だがよ、ここまで来て引き返すのか? 奥に行きゃ、デウスシステムが隠してる何かがわかるかもしれねー」
「でも……」
「お前は知りたくねーのか? 心配すんな、すぐに戻る」
一旦沈黙したのち、ヨルハはため息を大げさについた。
「わかったわ。すぐに戻ってね」
「任せろ」
(つづく)











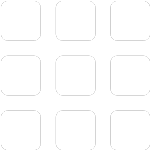








コメントを書く