壱
6月8日。
凍えるような寒さなのだろう。
俺は密着型宇宙服を着ているおかげで常に快適な温度を保つことができるが、旧人類たちは鹿や熊からはぎ取った毛を服代わりにしているので、死ぬほど寒いに違いない。
俺は吹雪が吹き荒れるなか、雪原を目的地もわからずに歩き続けていた。
俺の前には、10人ほどの旧人類たちが体を震わせながら歩いている。
この10人は、俺たちが最初に見た赤ん坊たちだ。
まだ10ヶ月ほどしか経過していないが、彼らはすでに初老を迎えているように見える。
肌はただれ、顔には無数の皺が走っている。
ヨルハは俺の数十メートル後ろから、小型宇宙船を走行式に切り替えて、ついてきている。
「こいつら、どこ向かってんだ?」
吹雪は強くなり、ほとんど視界が真っ白な状態だ。
旧人類たちは、どういうわけか背中に等身大の氷の人形を背負っている。
この人形たちは、俺たちが旧人類たちと接触して5ヶ月くらいのときから、突然作り出したもので、それを今、大事そうに運んでいる。
「わからない。レーダーによると、この先に別の洞窟があるみたいだけど……」
「別の? ってことは、そこに運んでんのか?」
「うーん……。ちょっと、待って。ブ、ブリザードよ! 伏せて!」
「おいおい、マジかよっ」
遠くから地鳴りのような轟音を鳴り響かせながら、強烈な嵐が俺たちにぶつかってきた。
俺は咄嗟に、一番近くを歩いていたひとりを抱えて、その場に伏せた。
背中を強風が通り過ぎていき、しばらく経つと、もとの雪原に戻っていた。
俺が庇った女は震えが酷かったものの、無事だった。
「大丈夫か?」
「レ、レキシ……」
女は立ち上がり、再び氷の人形を担ぎ上げた。
彼女は、ここ数ヶ月で最もかかわりの深い人物だ。
ことあるごとに、本を読みきかせ、そのたびに満面の笑みを浮かべていた。
そんな彼女も、老化してしまい、足腰も弱ってきたようだ。
「他のやつらは?」
「いえ、生体反応がないわ……」
「そうか……」
雪原の一部から、誰かの手が力なくとび出ていた。
どうやら、生き残ったのはひとりだけだったようだ。
弐
「なんの声だ?」
俺たちは以前いた洞窟とは違う洞窟の前に来ていた。
なかは真っ暗で何も見えない。
ただ、入り口は妙に大きく、大蛇の口のように横長に開いている。
洞窟を見つけ、旧人類の彼女は転んでしまった。
「おい」
俺は慌てて、彼女を抱き起した。
「レ……、キ……」
彼女は俺の肩を支えにして立ち上がった。
「あそこに行きたいんだよな?」
俺が洞窟を指さすと、彼女はこくりとうなずいた。
しかし、洞窟からは何かとてつもなく大きな生物の鳴き声のようなものが漏れていた。
さきほどのブリザードより、地を揺らすような尋常ではない鳴き声だ。
「ヨルハ、この洞窟、なかに何かいるのか?」
「いえ、大丈夫。何も生体反応はないわ」
「そうか……俺はなかに入ってくる」
「わたしも行くわ」
「いや、もし俺が戻れなくなった時のためにも、残っといてくれ。なかに何がいるかわかったもんじゃねーし。2人して行方不明じゃ笑い話にもならねーだろ?」
「……わかったわ。でも、何か危険があったら、すぐに連絡するか、引き返してきて」
「りょーかい」
参
手元のデバイスには、洞窟の入り口からどれほど歩いたのかが表示されている。
デバイスによれば、すでに300メートルほど歩いているようだ。
洞窟は少しずつ地下へ続いているようだった。
無数の氷柱が頭上にぶら下がっており、地面まで降りてきているものまである。
旧人類の彼女に肩を貸しながら、手元のデバイスで洞窟を照らして前に進んでいく。
奥へ進めば進むほど、何かの鳴き声は大きくなっている。
いったい何が住んでいるんだ。
そこに行けば、こいつらが必死で運んでいるこの氷の人形の意味がわかるのか。
いくつもの疑問が頭のなかに螺旋を描いて、回り続けている。
長く続いた下り坂が終わり、ひらけた空間に出た。
「レキシ!」
彼女は興奮した様子で、氷の人形を抱え、なかに走っていく。
「おい! なんだってんだ……」
俺は手元のデバイスの明かりの出力を最大まで引き上げた。
目の前に広がった光景に、俺は茫然と立ち尽くすことしかできなかった。
(つづく)











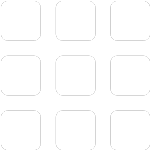








コメントを書く