三島看世の手の甲には血が放射状に広がり、まるで血管がそのまま外に浮き出てしまったかのようだった。
不必要に鮮やかで艶やかな血しぶきが、テーブルの上を舞っていた。
彼女の手に突き立てられたフォークは勢いを失い、その場でゆっくりと重力に押されながらテーブルに倒れた。
彼女は、そのフォークを再び拾い上げて、満足げに私の顔を覗き込んだ。
撫でまわすような、目つき。
坊主頭の魅力などまるでない女。
幽霊や妖怪の類にしか見えない複雑怪奇な女。
だが、その狂気はもはや、違和感や不快感を通り越し、私の心臓をわずかに揺り動かし始めていた。
それが愛に分類される感情なのか、憎しみに分類される衝動なのか判別をつけることは難しい。
むしろ、彼女の前ではすべての感情が過剰。すべてが過剰であるがゆえに、すべてが平等でもある。
「本来、食べ物を食べる目的で使用されるフォーク。けれど、人によってはわたしのように、凶器として使う場合もある。わたしにとって、今この瞬間、このフォークは自分を傷つけて、痛みによって自身の存在を明らかにする道具という意味合いがあるの。それがわたしが、このフォークに対して行う意味付け。意味なんてこうして移り行くもの。最初から絶対の意味を持っている物なんて存在しない。誰かが勝手に意味を付けているだけ。これが人の特徴。人は何も意味のないところに、勝手に意味付けをするの。動物はそこにあるものを、そこにあるものとして認識するだけだけど。わたしたちは意味を付けずにはいられない。たとえその意味で自分を苦しめることになってもね」
「……」
「意味付けには2種類あるの。1つは今のような個別的な極めて個人的な意味付け。もう1つは、世間が行う意味付け。フォークは食器だという世間が勝手に言っている意味付け。人はここに苦しむの。周囲と比較して、世間と自分との間にある意味付けの違いや差を直そうと懸命になる。そうして、どこの誰が決めたのかも不明瞭な意味に縛られることになる。あなたもそうでしょ? 医者という意味に縛られている、自分が優秀だという価値観に縛られている、社会的地位によって自分を意味付けている。でも、それって凄く空虚だと思わない? だってその意味付けはあなた自身から発したものかしら? 違うはずよ。あなたは自分が空っぽだから、他者から意味付けされることで、自分の意味を確立しているに過ぎないんじゃないかしら? あなた自身があなたを規定したことがあるのかしら? あなたの規定概念はあなた以外の人間や社会から与えられたものに過ぎないんじゃないかしら?」
フォークは血の線を作りながら、テーブルの上でくるくる回されている。
それはまるで、私の思考、私の感情、それらを表しているかのようでもある。
緊張でのどが絞まる。彼女の言葉の一つひとつが、私を構成する概念を徐々に瓦解させていく。
「……まるで自分だけは特別だと言いたげだな」
「特別……そうね、そうかもしれないわね。けれど、それはわたしが優位だとか、そういう優劣関係の話ではないの。わたしはただ、羨ましいだけ」
「羨ましい?」
「あなたたちは社会や他者と交流することで、意味付けをし合い、自身の存在を確定させていく。自分が何者であるかを他者から限定される。それはある種苦しみでもあるけれど、その干渉は歪んでいようが何であろうが、一種の愛情とも言えるわ。わたしにはその意味付けをしてくれる存在がいない。社会からも他者からも隔離されたこの場所では、わたしは誰からも規定されないし、わたしは誰にも干渉することができない。干渉することができなければ、愛は成立しない。だから、あなたたちのように意味に縛り付けられている生活は、羨ましくもあるの……でもね、今はあなたがいるわ、丸山先生」
彼女はフォークの先についた血を舌で綺麗に舐めりとる。
血の流れ出る手の甲を私のほうに向けて、微笑む。
「先生、これ処置してくれないの?」
血が指先を伝って地面にぽたぽた落ちていく。
自分でやっておきながら、私に処置を施せというのかこの女は。
だが、これを放置してあとで、霧山院長に知られるのも面倒だ。
私は仕方なしに、彼女の手を掴んで止血処置を施した。
もしかしたら……、いや、これは勘違いの一種だとは思うけれども、医療行為を行えない私に彼女は手を差し伸べたのかもしれない。
あえて自分を傷つけることで、私に医者としての仕事をやらせたのかもしれない。
そうして、彼女は私に医者としての意味付けを行ったのかもしれない。
考えすぎか……
「ありがとう」
私の妻や娘を死に追いやった女。
憎しみだけを増幅させるべきなのに、彼女の前ではあらゆる感情が前に押し出され、感情の優劣関係がつけられない。
憎悪だけでなく愛情も顔をのぞかせ、私と彼女の間には奇妙な愛憎関係が展開されていた。
彼女との不可思議なやり取りを済ませて、私は再び廊下に戻った。











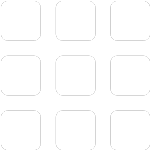








コメントを書く