205号室。
ドアを開けたその刹那、
部屋には白い雪が舞っているように見えた。
だが、それは雪などではなく、バラバラに千切られた原稿用紙だった。
吹雪のように舞う原稿用紙の残骸が、患者の姿にモザイクをかけている。
彼女は自分で原稿用紙を引き裂いて、空中へ放り投げている。
「違う、違う、違う、違う、違う!」
彼女は壊れてしまったかのように、机を叩く。
1人用の病室にしては不必要に広い空間に、原稿用紙の切れ端が舞う。
一瞬、茫然としていたが、私は現状をなんとかするべく、彼女へ声を掛けた。
「あの……」
彼女の動きはピタリと止まり、
舞っていた紙切れは、力なく地面へ落ちていく。
紙切れのカーテンが無くなり、ベッドに座る彼女の横顔がはっきり捉えられた。
若い女性。純白の院内着を身に付け、ベッドの上で項垂れている。
髪の毛は一切なく、坊主頭だ。
無造作に切られたためか、自分で毟ってしまったためか、髪の毛の長さが一定ではない。
禿げている個所も見られる。いや、剥げていると表現する方が正しい。
院内着に勝るとも劣らない白い肌。
白すぎる肌。透明に近い白。存在の不確実性を物語るような白。
私は圧倒されてしまっていた。
「わ、私、本日から担当になります丸山……」
そこまで口にしたところで、被せるように彼女は話し始めた。
「知ってるわ。丸山道尾先生でしょ?」
彼女の横顔が奇妙に吊り上がった。
「は、はい。ご存知でしたか。それで、申し訳ありませんが、お名前を伺ってもよろしいでしょうか? 外のネームプレートが読めませんでして……」
沈黙。
この空間だけ時間から取り残されてしまったかのように、静寂が流れた。
粘度の高い汗が、背中をなぞる。
突如、空気を引き裂く笑い声。
「あはは!!!! わたしの名前? 面白いわね……。わたしの名前、それはね……」
彼女はベッドから一本一本足を丁寧に下ろして、
粘着質に起き上がった。
笑うのを堪えようとしているのか、唇を噛んでいる。
震える唇からは血が滴り落ちている。
彼女はそれまで床に向いていた顔を、私のほうに向けた。
目が合った。瞬間、全身に鳥肌が立った。
こいつは危険だ。
意識ではなく、体が本能的にそう訴えていた。
唾を一口飲み込むまでもなく、彼女は目を合わせたまま駆け寄ってきた。
「あ」
声が漏れただけで、私はなんの抵抗もできなかった。
知らぬ間に、私の体は彼女に押し倒されていたのだ。
地面に倒れた私の体には、彼女が馬乗りにして跨っている。
彼女の唇から垂れる液体が、私の瞳に落ちる。
私の瞳は鮮血に染まっていく。
彼女の手には万年筆が握られている。
彼女はなんの迷いもなく、その万年筆の先を私の瞳に振り下ろしてきた。
私は咄嗟に意識を取り戻し、その腕を掴んだ。
寸でのところで万年筆は動きを止め、私の瞳の上でブルブルと震えている。
「な、なにを」
彼女の恍惚とした瞳には、私の無様な姿が映し出されていた。
彼女の肌には、皺もシミも一切ない。
しかし、なぜだろうか……
彼女の白さからは、ある種の濁りも感じる。
白濁とした純白とでも言えば良いのか。
真っ黒な瞳を携えた真っ白な肌。
混然一体となった混沌が具現化したような生き物。
こんなにも美しいのに、私は彼女に対して何も感じない。
「あら、寂しいわ。本当に覚えていないのね。プレゼント渡したでしょ?」
一瞬にして、あの日の出来事が蘇った。
不可思議な少女。意味不明な手紙。母が死んでもなお笑っていたあの少女。
「み、し、ま……これでも思い出せない?」
「みしま……みしまって」
そんな、そんな偶然、あり得ない。
なぜ、どうして……
「あなたが殺した三島美佐の娘。どう? 思い出してもらえたかしら?」
私が10年前に殺した愛人。
その娘、三島看世。
三島美佐とその夫、三島五郎の間に生まれた女。
当時8歳だった少女。10年経てば、ここまで成長していても不思議ではない。
ペン先にインクが溜まり、今にも眼球に垂れてきそうだ。
「あなたのせいで、わたしの人生滅茶苦茶。母を愛していた父は、その愛情を私に向けるようになった。どういう意味か分かるかしら? 私はその愛情に応えるために、父を殺したわ。そうしなきゃ生きていられなかったの。それから、ずーっと私はここに閉じ込められているの。でもね、あなたに感謝していることもあるの……」
彼女はまた不敵な笑みを浮かべた。
唇から涎と血が垂れて、私の瞳に侵入してくる。
白濁した液体と血が混ざりあい、私の視界は歪みきっていた。
「私ね、あなたが与えてくれた憎しみという感情のおかげで、作家になれたの。黒部夜目という作家に」
彼女は高らかに笑った。窓ガラスを割る勢いで、大声を張り上げた。
私が殺した愛人。
その娘が『第三の瞳』の作者だった。
それまでの恐怖感に加えて、私の心にはどうしようもない憤りが姿を見せ始めていた。
窓から差し込む月明かりが彼女の愉悦に浸った白肌を照らしていた。











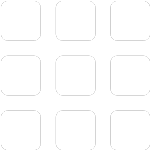








コメントを書く