視界に桜の花びらが横切った。
季節は春。
新入生ガイダンスを終えた1年生たちが、資料の入った手提げ袋を持ちながら、講堂の外へ出てくる。
講堂の外には、2年生以上の先輩方がずらりと並び、新入生を勧誘していた。
数えきれないほどの部活やサークル。
1年生たちはみな、友達とどのサークルへ入るか楽しげに相談している。
それもそのはず。
このサークル選びが、大学の友人関係構築には重要なのだ。
ここを失敗すると、友達のいない寂しい独りぼっちのキャンパスライフを送ることになる。
ゆえに1年生も必死だ。
その中に、立己仁(たつみ じん)はいた。
騒々しい勧誘の声、姦しい女子大生の声、
そのどれもが、仁にとって新鮮で、心地よいものだった。
他の多くの大学生と同じように、仁も輝かしい大学デビューを飾るため、
先輩から声を掛けてもらうのを、今か今かと待ち構えていた。
しかし、彼はどうしようもないくらい的外れな男だった。
そのせいで、仁の額には焦燥感からくる汗がにじんでいた。
「なぜだ……なぜ誰も声をかけん」
仁はブツブツと独り言を言いながら歩いている。
講堂前にできたサークル勧誘の商店街と化した道を歩けば、1年生は問答無用で声を掛けられる。
「ぜひ、うちのサークルへ!」と言われ、連れて行かれるはずだし、実際にそうなっている。
けれど、仁に声を掛ける者は1人としていなかった。
「一体何が問題なのだ? 我はもうこの通りを20往復はしているぞ。我はシャトルランをしにきたのではない。青春を謳歌しに来たのだ。なのに、なぜなのだ……」
なぜ声を掛けられないのか、そこに気付かない辺りに、その原因がありそうだ。
というのも、仁の格好は実におかしかった。
仁はスーツ姿で、ぼさぼさの頭のまま、額と背中に電子機器を張り付けていた。
仁の額にはテープで固定されたスマートフォン。
背中にはTシャツに張り付けられた大型のタブレット。
両方の画面に、「1年生です。声を掛けてください」の文字が流れている。
「我はどこからどう見ても1年生のはずだ。そう、文字通り、ピカピカの1年生のはずだ。なのに……」
サークル勧誘の列が終わり、仁はもう一度引き返そうとしていた。
「これで、21往復目だ」
その時、横から白装束の男が仁へ声を掛けてきた。
「君、1年生?」
初めてのことに、仁は嬉しさで舞い上がりそうだった。
仁は姿勢を正し、その男へ敬礼した。
「は、は、は、は、は、は、は、は、は、はい。いかにも! 我は1回生である!」
「は」の10コンボ達成。
驚異的なドモリ方である。
「あはは、君おもしろいね」
「それは良かったと存じ上げます!」
良く分からない敬語を使った後、仁は目の前の男を見た。
男の手には何やら分厚い本が握られていた。
良く見ると、神父のような格好をしている。
男は仁を見つめて優しく微笑んだ。
「私たちと一緒に悪魔を退治しませんか?」
宗教勧誘だった。
仁は細い目で、男を見つめた。
「このタイミングで宗教勧誘をしてくる……貴様こそ悪魔だ!!」
そんなこんなで、20分経過してもまだ仁に声を掛ける者は現れなかった。
35往復目となり、仁の足も限界を迎え始めていた。
清々しい表情で楽しげに先輩方と話す同級生を横目に、仁は1人で汗を垂らしながら歩き続けている。
「くそ……大学デビューとは、こんなにも困難な道のりなのか。他の連中はなぜ、話しかけられるのだ? 何か特殊な訓練でも行っているのか?」
そんな哀れな仁の前に救世主が現れた。
仁はふいに肩を叩かれ、体をビクつかせながら振り向いた。
そこにはミディアムショートの可愛らしい女子大生が立っていた。
ブーツからわずかに覗く靴下。
決して派手とは言えない白黒のボーダーTシャツ。
膝上を揺れ動く紺色のスカート。
小脇にはパステルカラーの鞄を抱えている。
「君、新入生だよね? 大丈夫? 汗凄いけど……」
「は、は、はい! 大丈夫であります!」
その女子大生は、ハンカチを取り出し、仁の額に流れる汗を拭きとった。
仁は硬直してしまった。
普段、女性とまともに話さない仁に、今のスキンシップはハードルが高すぎたのだ。
「あの、良かったら、うちのサークル来てみる?」
「え?」
「嫌だったらいいんだけど」
仁は放心状態に陥った後、嬉しさのあまりその場に土下座していた。
「感謝いたす! 心から感謝いたす!」
「えー? どうしたの? ちょっと……顔上げて」
周りから好奇の視線が集まる。
女子大生はしゃがみこんで、仁の顔を覗き込む。
「ええっと、あたし倉本愛里(くらもと あいり)2年生です。よろしくね」
「我は立己仁、1回生である! よろしくである!」
「ふふ、変な喋り方」
愛里の砕けた笑顔を、仁は神々しいものでも見るかのように眺めた。
愛里の笑顔を目の当たりにして、仁は鼻血を垂らした。
「え? だ、大丈夫?」
愛里はティッシュを取り出し、仁の鼻を慌てて拭いていく。
これが彼――立己仁の――青春の幕開けだった。
(つづく)











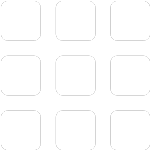








コメントを書く