1
ネオン輝く新宿――歌舞伎町。
平日の夜ですら、眠ることを知らないこの街には、夜の匂いにつられて、多くの人々が集まっていた。
左右から降り注ぐ光と、四方八方から飛び交う笑い声、叫び声、泣き声に、仁は面食らっていた。
15名ほどの大学生の団体が、いくつかの塊を作りながら、幅をとって歩いており、
仁は黙ってストーカーのように、その集団を追尾することしかできずにいた。
そんな輪に入れない仁を見かねて、前方を歩いていた愛里が声を掛けてきた。
「立己くん、こういうの慣れてないかな?」
「慣れてないでございます!」
またもや意味不明な敬語を垂れ流す仁である。
下から覗き込むようにして、仁の様子をうかがう愛里。
その麗しい唇の動くさまを見て、仁は思わず目を逸らした。
「で、でも、大丈夫でございます! この苦難、自力で乗り越えてみせるのである」
仁はガッツポーズして下手くそな苦笑いを愛里に向けた。
「ふふ、面白いね、立己くんは」
口に手を当てて笑う愛里。
笑うたびに揺れる肩を見ながら、仁は息を整えるのに必死だ。
「それにしても、その服……」
愛里は仁を下から上に眺めた。
仁はどういうわけか、全身金色の派手な服を着ている。
首にはヒョウ柄のスカーフを巻きつけ、色付きレンズのサングラスを掛けている。
仁としては、気を遣ったつもりなのだ。
流行りの衣装を考えて浮かんだのが、ピコ太郎しかなかった。
若者に受けるためには、インパクトを与えねばという彼なりの自己紹介なのだが……
そのせいで、人気者になるどころか、完全にドン引きされてしまったのだ。
「……いかすね」
愛里は苦笑いを浮かべながら、親指を立てた。
気遣いに長けている愛里ですら、顔を引きつらせるので精一杯のようだ。
しかし、仁はというと、お世辞を理解できるはずもなく、
ホメられたことで、心臓が胸骨を突き破って飛び出てしまうほどに興奮し、口を押えていた。
「歓喜のあまり、危うく吐血するところであった」
先頭の集団から「愛里ちゃーん!」というご指名が入り、愛里は「ごめんね」と手を合わせてから、仁のもとを離れた。
愛里が一番先頭の集団へ移動したあと、
集団の後方で歩いていた仁と同じ1年生の大学生2人が、
愛里についてヒソヒソと話しているのが仁のほうへ漏れ聞こえた。
「愛里先輩かわいいよなぁ……なんか、しつこくない可愛さっていうかさ」
「でも、結構、男関係とか激しいらしいぜ? いくつもサークル掛け持ちしてるのも、いい男探すためみたいな噂もあるし」
「そんなに掛け持ちしてるの?」
「なんでも、うちの大学だけでも10以上のサークルで、飲み会の幹事とかしてるみたい。ほかの大学と合わせるともっとすごいらしい」
「へぇ、じゃあ、ライバル多めかぁ」
「お前じゃ無理無理」
話の一部始終を聞いて、仁は立ち止まっていた。
まるでオーギュスト・ロダンの『考える人』のように、その場で空気椅子をしながら考え込んでいた。
ピコ太郎の衣装を着た大学生が、眉間に皺を大量発生させていた。
「うむ……」
わずかに視線を上げた仁の視界には、前方で先輩たちに囲まれながら、満面の笑みを浮かべる愛里の姿があった。
「愛里殿……」
2
テーブルに置かれたグラスの水には、揺れる仁の顔が映されていた。
振動するテーブル、振動する空気……
アルコールを含んだ酸素と二酸化炭素が、室内に滞留していた。
長テーブルに会議をするが如く15人の学生が並んで座り、各々に会話を楽しんでいる。
小さな居酒屋ということもあり、客はそこまで多くはないものの、
学生を中心にそこかしこで飲み会が繰り広げられている。
飲むときのコールやら、恋愛話やら、怒鳴り散らすように言葉を交わす。
一番端の席に座った仁は、ただ茫然とグラスに注がれた水の動きを眺めることしかできなかった。
ここにきて、自分は場違いだと、ようやく気づいたようだ。
ピコ太郎の来る場所ではなかったのかもしれないと、やっと理解したようだ。
そんな仁を見かねてか、愛里が声をかけてきた。
「立己くん、大丈夫? 顔引きつってるけど?」
「うむ……。笑顔を作ろうと練習はしたのだが、なかなか愛里殿のようにはできぬ。世の中うまくいかぬものだ」
以前、家でやっていたように笑顔の練習をしていた。
面白い話ができないのであれば、せめて笑顔だけでもという努力なのだが、愛想笑いは仁が一番苦手とするものだった。
「え?」
困惑する愛里。
そこへ、ビール片手にスーツ姿の男が近づいてきた。
4年生の坂下先輩である。
就職活動の面接の帰りらしい。
坂下は馴れ馴れしく、愛里の肩に腕を回した。
その生臭い息を吐きかけながら、愛里の体を撫でまわす。
「愛里ちゃーん。そんなキモイのと話してねーで。俺のこと相手してくれよぉ」
「……あはは、先輩。なんか赤ちゃんみたい」
愛里は笑いながらも、体を強張らせていた。
困り果てた愛里を目の当たりにして、仁は坂下を睨みつけた。
(つづく)











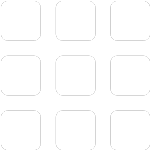








コメントを書く