無礼講。
なんて言葉は、時にセクハラの言い訳として流用されるわけだが、
仁の隣の席ではまさに、そういう事案が発生していた。
4年生の先輩、坂下。
今回の飲み会で最年長の先輩だ。
女癖の悪さで有名である。
見た目は白い顔のいわゆる「塩顔」なので、優れた容姿といえる。
その坂下は愛里の後ろからおぶさるように抱きついて、腰やら首やらに手を這わせていた。
愛里は笑いながらも、いやそうに体をよじらせた。
その動きが坂下の征服欲求を刺激する。
坂下は愛里の腰をなぞりながら、胸のあたりに指を移動させる。
「愛里ちゃん、ほんとちょーかわいいわ~」
「先輩ちょっと……」
「なぁ、もっと構ってよぉ。俺、今日面接ちょー頑張ったんだぜ?」
「お疲れ様です。先輩とはもういっぱい話したじゃないですか。ほかの人とも話したいんですぅ」
「このキモイやつと?」
坂下は見下すような視線を、仁へ向ける。
「てか、こいつ酒飲んでねーんだろ? 飲めよバカ」
仁は微動だにせず、即答する。
「飲まぬ」
「あ?」
「未成年の飲酒は法律で禁止されている」
「でたでた! こういうやつ! 空気悪くすんなや」
「法律を無視し、社会を悪くするよりマシだと思うが」
「うわ、めんどくせー。やっぱこいつ、つまんねーわ。愛里ちゃん。俺ともっとお話ししようぜ」
坂下は懲りずに、今度は愛里のふくらはぎに手を伸ばす。
「ちょっと! 先輩、本当に……」
「しってるぜ? 愛里ちゃん、男あさってんだろ? 俺が相手してやるって。大学入ってから、50人以上の女と付き合ってきたし、俺にゆだねりゃ気持ちよくなるからさ。ほかの男じゃできねー本当の愛し方ってやつを教えてやるよ。なぁ? ちょっとその気になってきたろ? なぁ2人だけで愛を語りあおうぜ」
「ちょ、ちょっと……」
坂下のなめくじのような手が愛里の股に差し掛かろうとした、その時、
愛里の隣から爆風が吹いた。
いや、爆風が吹くほどの強烈な爆笑が聞こえてきたのだ。
「だあああああ、はっはっはっは!!!!」
騒々しいはずの店内に、仁の化け物じみた笑い声が響き渡った。
それは大ホールで、一番後ろの観客席まで声を届かせるオペラ歌手のような重厚な声だった。
仁が声を上げるたびに、空気中に声の波が広がり、近くの人間は吹き飛ばされそうになる。
ひとしきり笑い終えると、周囲は静寂に包まれていた。
誰もが仁に注目し、坂下ですら、慄いて愛里の体から手をどけていた。
仁は盛大に拍手をし始めた。
「あい、あい、あい、あい……お猿さんか、貴様は」
「は? てめー、何言ってんだ? 急に笑い出して、気持ちわりぃ……」
「愉快! 愉快! 愉快! きわめて愉快! いやはや、坂下殿はご冗談がお上手だ!」
「冗談?」
「いかにも。坂下殿は先ほどこう言った。『俺はこれまで50人以上の女と付き合ってきた』と……」
「ああ。てめーみたいな根暗と違って、俺モテるからさ」
「いやはや、お見事だ。つまり坂下殿、貴殿はこれまで50回も同じ失敗を繰り返してきたというわけだ」
「なんだと?」
「50回付き合ってきたとは、要するに50回うまくいかなかったという意味ではないかね?」
「……」
坂下は黙って、拳を握っている。
「我は最初、坂下殿は自慢をしているとばかり思っていたのだが、これは失敬。自慢とみせかけた自虐であったとは。自ら道化を演じて、笑いをとったのだろう? これを見事と言わずなんという?」
仁の挑戦的な上目遣いが、坂下の怒りを駆り立てていく。
「てめー、俺をバカにしてんのか?」
坂下の美しい顔に、青白い血管が浮かび上がる。
「バカにするなどとんでもない……ただ……」
「ただ?」
仁は一度うつむいてから、最上の笑みを坂下へ向けた。
「蔑んでいるのだよ」
それは、いままで練習していた笑顔とは比べ物にならないくらい、完璧すぎる満面の笑みだった。
「この野郎!」
坂下の怒りは頂点に達した。
握られた拳は、主の許しを得て、仁の横顔を襲った。
骨に響く鈍い音。
殴り飛ばされた仁の体は、テーブルの上を滑り、グラスをなぎ倒していった。
倒れた仁の胸倉をつかみ、坂下は3回4回と拳を仁の顔面に叩きつけた。
「キモイ! キモイ! 死ね! 死ね!」
酒が完全に回ってることもあり、坂下の怒りは体中に循環し、制御不能だった。
それでも、仁はニコニコ笑い続けている。
ひとしきり殴り、疲れ果てたところで、坂下は財布から金を出し、仁の顔に投げ捨てた。
「思い知ったかくそ野郎。くそ、興ざめだ」
坂下はふてくされながら、金だけ置いて店を出て行った。
仁は腫れた顔のまま、投げつけられた5000円札を握って、見つめていた。
「これで良かったか? 新渡戸稲造よ」
新渡戸稲造ではなく、樋口一葉だ。
というツッコミができるほど、温和な空気は漂っていなかった。
それでも、仁の姿を見ながら、愛里は少しだけ笑みを浮かべていた。
それは愛里にしては珍しい、実に素朴な笑みだった。
(つづく)











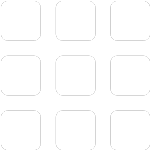








コメントを書く