世は大正時代-
私には文通相手がいる。
それは、働く甘味屋に偶然訪れた男性の兵士。
ある日、1人の若い男性の兵士が店を訪れた。
「ふう」と息を吐きながら店の縁側に座ると、団子を頬張り、お茶を飲んだ。
私が暖簾越しに彼を覗くと、店の前に咲く桜を見上げていた。
「綺麗ですよね。」と私は声をかけた。
彼は私を見ずに『花を見ると癒される。この団子も花に負けていないけれどね。』と呟くように話した。
そして私の方を振り向くと『隣にも花が咲いていたようだ。』と笑いながら言った。
言われ慣れないことに恥ずかしくなり頬を染めると、『桜のようだね。』と彼は話す。
私は照れを隠すため、彼の饒舌さに感心したように「お話が上手なのね。」と返した。
その後も2人で桜を見ながら他愛もない話をしていたが、彼はふと懐中時計を開くと、
『数十分の短い間しか店に滞在することができず残念だ。』
と帰り支度を始めた。
私は「また店に来たら、お話しましょう。」と声を掛けた。
彼は私の目を見ながら無言で頷き、店を後にした。
次に彼が店に来てくれた時には、話し足りない話題を事前に
手紙に書いておき、渡せばよいと考えていた。
そこから私達の手渡しの文通は始まった。
彼は色々な場所に遠征に行き、訓練をしているようで月に1度、この街と甘味屋に訪れてくれた。
手紙を渡すと彼はとても喜んでくれ、自分も返事を必ず書くと話してくれた。
それから毎月、彼が店を訪れた日には、ひと月の出来事を手紙に記して送りあった。
最近の街での出来事、訓練で訪れた地域の話、季節の移ろいの話、今後の日本の未来の話、
沢山の話をした。
交換した手紙は10通になったが、その中でお互いに対する気持ちを記している手紙は無かった。
店の中で出会うほんの僅かな時間の中で、目を見合わせるとお互いを思う気持ちは同じような気がしていた。
私は会うたびに強く逞しくなっていく彼の体に、悪い不安が過ぎりつつも胸は高鳴っていた。
彼と親しくなり1年が過ぎた頃、第一次世界大戦が始まり、日本軍はロシアに出兵した。
私は、ただ国と秩序を守るための戦いを見守ることしかできなかった。
唯一できることは、大好きな人の無事を信じて、国の平和が訪れることを祈ることだけだった。
それから、2年、3年、4年が経った。
彼が甘味屋に訪れることはなくなっていた。
人伝いに彼の戦死の知らせを聞いた。
一つの戦争が終わると日本の若い男性の多くが亡くなっていた。
季節は移ろいゆく。
今年も冬が終わり春が来ていた。店前の桜の木は、毎年変わらずに綺麗に花を咲かせる。
静かな街にサラサラと川が流れる音と、鳥のさえずりが響きわたり、のどかな春の訪れを告げる。
春の桜の如く儚く散った私の恋。
地面に散っていた桜の花を1つ拾い、最後に送る手紙に包んだ。
投函するためポストに向かったが、思い留まった。
最後の恋文は、甘味屋の前を流れる川に流すことにした。
遠くにいるあなたにしっかりと届くようにー
『本当はいかないでほしかった。
あの年と同じように、今年も桜の花が綺麗に咲いたように、
人の思いとは裏腹に時は過ぎていってしまう。
返事はいりません。
さようなら、そしてありがとう。やさしい私の初恋の人-』











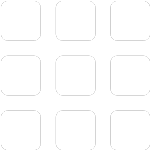








コメントを書く