僕には付き合って3年の彼女、美沙紀(ミサキ)がいる。同棲を始めて2年になるが、彼女は家のことを何でもやってくれる。ゴミ捨て、炊事、洗濯、掃除…全てを卒なくこなしてくれる。僕がやるようなことはほとんどない。僕が自発的にやる前に既にやってくれている。
しかも美沙紀だって働いているにもかかわらず、だ。
僕はただの会社員ではあるが、それなりの所得はある。おそらく美沙紀が仕事を辞めても2人で余裕で暮らせるくらいは稼いでいる。ただ、それだけ働いている分、休日の僕は家でゴロゴロしていることも多く、美沙紀との時間といえば2週間に1回くらいデートと称して最寄りの駅まで買い物するくらいだ。
正直な気持ちを言ってしまえば、美沙紀は彼女というよりも…家族?親友?
美沙紀はとてもいい女だ。しかし僕にとってはただ都合が良い女なだけなのか―。たまにこんな最低な自問自答をししまうほど僕には勿体ない彼女なのかもしれない。
美沙紀の性格はおとなしめ。口数も少ない。化粧っ気が無いわけではないが、職場でも友達でも他の男の気配は感じられない。僕は束縛するタイプではないので、もうちょっと男友達が居ても良いのではないかと思ってしまうが、美沙紀はそういう交友関係に関心やコンプレックスが無いようだ。リア充という概念も持ち合わせていなそうだし、LINE以外のSNSはしていない。
僕が家でゴロゴロしている休日は、女友達と買い物に行ったりもしているようだが、帰宅すると楽しそうに毎回細かく僕に報告してくる。報告内容は浮気なんぞ疑う余地もないくらい細かく、お土産なんかも買ってきれくれる。これで隠れて浮気や他の男と会っているのであれば、むしろ称賛に値するほどだ。
美沙紀は見た目が可愛らしく、とても女性っぽいせいか、多分他の男からもモテるに違いないと思う。僕と街を歩いていても、若い男性にチラチラ見られているのは僕の目から見ても分かる。しかし本当に異性に関することはどうでも良いようだ。僕から言わせれば出家したのかと思うくらい他の男の目を気にしていない。
そんな日々を繰り返していたある日、僕は仕事中に美沙紀から話があると連絡が入った。内容は「今夜、近くのレストランで会えないか」ということだった。
時間的にも場所的にも問題はなかったのだが、平日の、しかも当日に、いつも家で一緒にいる彼女から外で会いたいだなんて…。僕は正直、別れ話だと予感した。
同棲を始めて2年。結婚すらしていないのに家でゴロゴロしている僕。家事は全て自分でやりながら、毎日ヘトヘトな生活。こんな生活がこれから何十年も続くことを考えると…そりゃあ、僕とは一緒にいたくなくなるに違いない。僕が美沙紀の立場だったらすぐに別れたいくらいだ。
だから僕は美沙紀に「分かった。心して行くよ。」とだけ返信した。美沙紀にとって、僕から離れることが幸せなら、それは素直に受け入れることが僕の罰だと思いながら―。
夜、僕は時間通りレストランに到着した。そして席に目をやるなり驚いた。そこには普段見ることのない余所行きの派手な服と顔をした美沙紀が座っていた。
さらにサプライズは続いた。僕が席に座り、店員が水を置いて立ち去るなり、美沙紀が一言。「ふぅ~…今日は言いたいことがあるの。でもちょっと待ってね。」
そう言うと美沙紀はテーブルの上に2つだけ置いてある水の入ったグラスのうち、自分の分だけを手に取り一気に飲み干した。
「えっと…こういうの我慢できないからすぐに言うね。あのね、私と結婚してください。」
僕はまさかの逆プロポーズを受けた。しかもあっさりと…。開いた口が塞がらないとはまさにこのこと。僕の頭は真っ白になった。
しばらくして、美沙紀はその想いを僕に語り出した。美沙紀がなぜ僕と結婚したいのかを切々と話してくれた。僕は全く意識していなかったのだが、美沙紀にとってはとても大事なことだったらしい。
それは、一緒に道を歩く時はいつも僕が車道側を歩くこと。
買い物をした時は必ず僕が荷物を持つこと。
毎日会社帰りに美沙紀にお菓子を買ってくること。
僕は美沙紀を責めるような発言をしたことがないこと。
美沙紀がしたいことは全て応援・援助してきたこと。
僕は自分よりいつも美沙紀を第一に考えていたこと。
それは僕自身も気づいていなかったことだった。そう…なんだかんだ言っても僕は美沙紀を愛していた。しかも、それが全て美沙紀に伝わっていた。
美沙紀にとって、それら全てが心地良く、同棲中の2年間、毎日が楽しかったと話してくれた。だから変に気負うのではなく、このままで良いからずっとそばにいてほしいと言われた。
僕はレストランにも関わらずその場で泣き出した。
そして、なんとか一言だけ振り絞って伝えた。
「僕もあなたと生きていきたいです。」











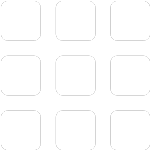








コメントを書く