街を散策し終えた私たちは、休憩のために喫茶店へ入店した。
窓際の席。外を歩く人々はすべてエキストラのように見えた。
いや、普段から自分に関係のない人間はたいていがエキストラにしか見えない。
むしろ障害物に近いと言っても過言ではないかもしれない。
満員電車や身動きの取れない雑踏の中で、ひとり1人を人間として尊重し認識できている者などいるはずがない。
人間はそこまで過剰な情報量には耐えられない。
ゆえに、目の前にいる対象を人間ではなく、「者」ではなく「モノ」として処理することにより、私たちは辛うじて健全な精神を保っていられる。
「ねぇ、丸山先生」
私の思考が窓枠を飛び出していたことに木ノ下雪は敏感に反応し、机の上に放置されたままだった私の手の甲に触れた。
指の腹をしっかりつけるのではなく、関節と関節の間に空気を含ませるようにして撫でる。
「丸山先生、元気出してください。せっかくのお出かけなんですから」
「そうですね……」
視線を彼女に戻す。
ところどころがバラや葉の形に薄く切り抜かれたレースの黒いドレス。
肌が透けて見え、淫靡な雰囲気を醸し出している。
服装に目がいくと同時に、久しく嗅いでいなかった女の甘い香りが鼻腔に侵入し、脳内のシナプスを直接刺激してくる。
「丸山先生、いい加減、その堅苦しい喋り方やめませんか?」
「え?」
「わたしもっと丸山先生と仲良くなりたいんです」
そう言って彼女は、私の脚に細長い脚を絡めてきた。
「……木ノ下さん」
「その呼び方もやめましょう。雪って呼んでください」
「しかし」
「えー、呼んでくれないの~」
彼女はまるで駄々をこねる少女のように、頬を膨らませて私を覗き込む。
メガネをした知的な女性が、まるで幼稚な子供のように振舞っている。
そして机の下ではいまもなお、いやらしい脚さばきが行われている。
知的で稚的で恥的だ。
「では、雪さんでどうでしょうか?」
「なんかその呼び方だと、昔の人みたい。でも、いいですね、それ。今日はいっぱい楽しみましょうね。実は丸山先生みたいなダンディな人、結構タイプなんですよ?」
「タイプだなんて、照れますね」
「ふふふ、やっと笑ってくれましたね」
そう言いながら、彼女は私の笑顔より何倍も出来の良い笑顔を向けてきた。
*
それから私と彼女は、ショッピングモールやら雑貨店やらを特に目的も持たず歩き回った。
その間も彼女は終始、明確なリアクションを私に返してくる。
何かを見るごとに驚き、喜び、はねる。
感情表現の教科書のように、彼女はひとつひとつ出来事に、それぞれの反応を提供し、私を楽しませてくれた。
時間が経るごとに、私の凝り固まっていた罪悪感は融解し、彼女の存在に包まれ、幸福感が芽生えつつあった。
ただ気になるのは、何者かの視線だ。
街を歩いている最中も、ずっと誰かに見はられているような異様な感覚を覚えた。
そんな違和感を覚えつつも私たちは、やたらとピンク映画やら恋愛映画やらしか上映されていない映画座のような場所で、古めかしい映画を観た。
シリアルキラーの女が自己否定感が強く自信のない男を次々と篭絡し、殺害していく狂った映画だった。
しかし、バイオレンスとセクシャリティの絡み合いは、私の欲望の最下層に刺激を与えていたようで、同じように影響されたのであろう彼女も、目の前の映画を観ながら何度も私の手に指を絡めてきた。
細胞が裏返るような快感を覚えた。
子供と手を繋いだ時とはまるで違う高揚感。
私たちは普段、社会的な人間として振舞っている限りは、細胞は表向きに体に張り付いている。
だが、こと異性との接触になると話は変わってくる。
社会では表向きに並んでいた細胞たちが裏返り、極めて感度の高い皮膚を形成するようになる。
このように、私たちの細胞には裏と表がある。
「おもしろかった~」
映画館を出ると彼女は、勢いよく伸びをした。
すでに夕方。日が暮れ始め、夕焼けが彼女の脇に魅惑的な影を作り出し、彼女の脚を過剰に赤々と照らし出していた。
「今日はとっても楽しかったですね? また一緒に来ましょうね?」
「ええ……もちろん」
「さて、時間も時間ですし、今日はもう帰りましょう」
「そ、そうだね」
名残惜しいからなのか、物欲しさからなのか、返事に動揺が滲んでしまった。
私のその様子を見て、何かを察したかのように、彼女は唇に指を立てて微笑んだ。
「……もしよかったら、あとでわたしの部屋来ますか?」
唾を飲み込むのと同じくして、私は小さく情けなく「はい」と頷いた。
しばらくは水分補給が必要ではないくらいに、唾液が口内を支配していた。











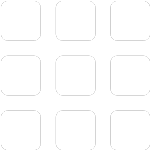








コメントを書く