壱
「はぁはぁはぁ……」
悪夢から目覚めて、私は騒々しい呼吸を繰り返していた。
ベッドから上体を起こして、左右を見るが、先ほどまで私を追いかけていたはずの不気味な瞳はどこにもない。
あれは夢だったのか、と朝日を浴びてようやく気付くことになった。
プルルルル、プルルルル……
内線だ。
ベッドわきの時計を見ると時刻はまだ朝の6時前だ。
私が担当する時間は、もっと遅くのはずだ。
こんな時間に一体何のようだろうか。
私は訝し気に受話器をにらみつけてから、仕方なしにその内線をとった。
「もしもし、丸山で……」
(出るのが遅い。ワンコール以内には出ろ、常識だぞ)
一体どこの誰が決めたの常識なのだ、それは……
この人の話に被せてくる異常にせっかちな声は、まさしく院長の霧山の声だった。
「申し訳ありませ……」
(それで、今日だが、さっそく働いてもらう。とは言っても、お前が医療行為をすることはない)
「それはどうい……」
(三島看世とミズの身の回りの世話をしろ。朝昼晩の食事と排泄介助。そして、三島看世は昼の散歩だ)
なに? 冗談じゃない。この私がそんな従者のようなことをしなければならないのか。
そんなものは、看護士の仕事だ。私の仕事は医者であり、高度な治療を施すことなのであって……
(そういうことだ、忘れるなよ。お前には、どこにも行き場所はない)
ツーツーツー……
電話は一方的に切られた。
本当に身勝手な男だ。
しかし、彼の言う通りでもある。
どういうわけか、私が家族の遺体を遺棄した事実をこの病院は掴んでいて、三島看世の母を殺したのが私だという事実も当然知られている。
ここを逃げたところで、私を少なくとも死体遺棄の罪で警察へ突きつけるのは目に見えている。
ここは、彼の言うことに従って、行動するしかなさそうだ。
それにしても、なぜ私が、自分の妻や娘を死に追いやった呪いの小説家を引き連れて散歩などしなければならんのだ。
不愉快を通り越して抑うつ状態になりそうだ。
私は心の中で不平不満を吐き散らしながら、部屋に併設されたシャワールームで体を洗い、準備を進めていた。
弐
盆に置かれた紙コップから水がはねた。
水滴はベッドに備え付けられたテーブルの上に飛散し、窓から差し込むどんよりとした光を反射させる。
水滴には相変わらず薄気味悪い笑みを浮かべる三島看世と、その笑みを苦々しい顔で受け止める私の表情が同時に映し出されていた。
三島看世の担当医に命じられてしまった私は、朝食を投げ捨てるようにテーブルに置いた。
病室には、外の朝靄以上の何某かの厭な湿気が充満していた。
三島看世は、ベッドに座りながら、私を見据えた。
「そんなに苦痛かしら?」
「何がだ? お前と話す気はない。さっさと食べろ」
「あら、酷いわ……。一応、あなたの患者なのでしょ? わたしは」
彼女の肩頬が奇妙に吊り上がった。
「……早く食べておけよ。私は失礼する」
私は彼女の視線から逃げるように、背を向けてドアに手をかけた。
「ここでは医者らしいことなんて何一つさせてもらえないわよ? 別の病院に移ったら? ああ、そういえばあなた人殺しだものね。普通の病院なんていけないわね」
彼女の吐息にも似た声は、私の背中をゆっくりとなぞっていく。
知性というよりも感性の刺激される独特な粘り気のある声の感触が全身にまとわりつく。
「人を殺しておきながら、医者としてのプライド、役割、地位、名誉、そういうものは守りたい。だから他の職を選ぶわけでもなく、ここを選んだのでしょ? 何もかも捨てられれば、医者に固執する必要なんてないものね」
反射的に拳の筋肉が収縮を起こし、爪が自分の手のひらに食い込んでいく。
「何が言いたい?」
「別に……。あなたも結局は意味付けに苦しんでいる哀れな生き物だと思っただけよ」
「哀れ? この私が?」
何を馬鹿な話をしているのだ、この女は。
私が哀れ? そんなわけがあるか。
幼少時代から誰よりも優秀で、一流の大学を卒業し、医者という確固たる社会的地位を獲得し、美しい妻と娘も手に入れた、この私が哀れ?
私は思わず振り向き、彼女をあの吸い込まれそうな眼球を睨みつけていた。
「人と動物の違いって何か、わかるかしら?」
「何わけのわからないことを……、そんなもの高度な知能があるかないかの違いだろ」
「それよりも大事な違いがあるわ。意味付けを行うか行わないかの違いよ」
「意味付け?」
「例えばここにあるフォーク……」
彼女はフォークをゆっくりと手に取る。
「常識的に考えれば、食べ物を刺して口に運ぶための道具よね。食器と言われるくらいだから、なおさらよね。けれどね、こうやって使ったらどうかしら?」
テーブルに飛散していた水滴たちに、血の色が滲んだ。
「な、何を……」
彼女は突如、持っていたフォークを自分の手の甲に突き立てたのだ。
血が流れ出て、透明だった液体たちはたちまち彼女の鮮血に染められていった。











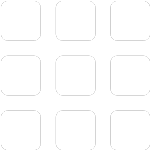








コメントを書く